| ●若さの泉 チベット体操 - 肉体の奴隷となっている人に自由な人はいない。 ・運動オンチな私でも無理なく毎日続けられそうなことを探していたらやっと出会えました。 ・著者のピーター・ケルダー氏は、公園でブラッドフォード大佐という退役軍人に出会います。 ・このときの大佐は60代。白髪を残すも頭ははげ上がり、歩くのにも杖を使っているくらい。 ・そして、インド赴任中に耳にした“若さの泉”を探しに、チベットへ行くので一緒に行かないかと誘われた。 ・ケルダーは同行しなかったが、大佐が帰国したら会う約束を取り付ける。 ・4年後、黒髪がふさふさした、背の高い壮年の男性がケルダー氏を訪ねてきた。 ・それは、かのブラッドフォード大佐だった。 ・そして、伝授されたのがこの“若さの泉”・チベット体操だった。 ・しかも、チベット体操は非常に簡単で、老若男女を問わず多くの人が行えるものだった。 ・「ヒマラヤ・クラブ」の集会をたちあげ、実践普及をしたところ効果があった。 ※かのプラス思考の元祖中村天風の師、カリアッパ師は「カルマッパ」と発音されており、この人物が同一人物であるとすれば、ラマ教カルマ・カギュ派の管長であるとのこと。カルマ・カギュ派はラマ教の中でも名門の宗派で、しかもチベット最高詩人と言われヨーガの大行者と言われたミラレパの流れをくむものも修行を積んできたところです。 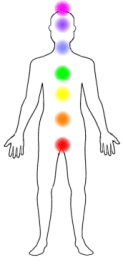 ●7つのチャクラ(エネルギーセンター、英語ではヴォルテックス、渦巻) ※かの女優シャーリー・マクレーンも著書でチャクラについて言及 ・強力な磁界 ・目には見えないが実在するもの ・ホルモンの分泌を促進する。 ・人体機能の全体を統制する。 ・健康体の場合にはチャクラはそれぞれが速いスピードで回転し、「プラーナ(気息)」または「精神エネルギー」と呼ばれる活力に満ちた生命エネルギーを製造し、内分泌腺をとおして上へ上へと送り出している。 ・回転するチャクラは健康な人であれば肉体を超えて外に向かって発散している。 ・チャクラの回転スピードを健康で強壮で調和がとれた25歳の男女のスピードで回転させることを目的とする。 ・7つのチャクラの中心はそれぞれが人体のホルモンを司る内分泌腺にある。 1番目-生殖腺 -赤-嗅覚。生存、生殖、生命力、 2番目-腹部の膵臓-オレンジ-味覚。創造性、感情、生きる喜び、 3番目-みぞおちの副腎-黄色-視覚。個性・知性、バランス、 4番目-胸腺 -緑、ローズ-触覚。心と体を結び、精神を高める 5番目-甲状腺 -青-聴覚。思考感情・コミュニケーション、 6番目-松果腺、 -藍-第六感。直感・洞察力 7番目-脳下垂体 -紫、白、金-すべて。永遠、霊的エネルギー ・これらのイメージが大切 ●5つの儀式 最初の1週間−信念を持つ。 朝か夜 各儀式を1日に3回から始める。 それぞれの回数を2回づつ増やす。 各儀式をフルに21回できることを目標にする。(4〜5ヶ月で達成) 続けることにより、ポジティブな心理効果が大事 息を吐く⇒緊張感がとれる。吸い込む⇒幸福感と満足感 1) 飛行機回り 手を平行に真横に開いて、目を開けて左から右へ時計回りに回転する。 チャクラの回転スピードを一気に上げる。 5〜6回。わずかにめまいを感じるところまで回転できればよい。 2) L字体操 ・固めのマットの上に仰向けに寝る。 ・両腕を体の両側面に沿って伸ばし、手のひらを床に置く。手のひらはまっすぐ、指と指の間は閉じる。 ・鼻からゆっくり腹式呼吸をしながら頭を持ち上げ、顎を胸にぴったりとつける。 ・鼻から深くお腹の底まで息を吸いながら頭を床から持ち上げ、顎を胸にぴったりとつける。 ・ひざを曲げずに、両足を床と垂直になる位置まで上げていく。 ・足が垂直の位置まできたら息を吐き切るまで口から吐きながら頭と足をゆっくりと床に下ろす。 ・ひざがまがらないように注意する。 ・呼吸のリズムを会得する。 ・首と脚を上げ下げすることで、腹筋と背筋も鍛え体内リンパの流れをスムーズにする。 3) L字上体そらし ・両膝頭と両足指先を支点として床にひざまずく。 ・ひざから上をまっすぐ垂直に立てる。 ・手はお尻の少ししたにある大腿筋に沿うようにあてがう。 ・頭を前に曲げていき、顎を胸にぴたりとつける。(息を吐いておく) ・息を吸いながら頭をできるかぎり後ろにそらし、同時に上体も後ろにそらしていく。(背骨は弓状) ・上体をそらすときに太ももに添えてある手で身体を支える。 ・充分にそらしきったら、息を吐きながら上体をもとの直立の位置へ戻す。 ・意識を自己の内部に向けるため、目を閉じて行う。 ・首周りの筋肉を鍛え生命エネルギーを鎖骨の辺りまで引き上げます。 ・内面を見つめることにより、老化は思い込みに過ぎないということを知る。 4) カニさん体操 ・両脚の足先を30センチくらい広げて前に投げ出して座る。 ・上半身は直立させ、手のひらを床につける。 ・足は直角にする。 ・息を吐きながら、顎を胸につけるようなつもりで前に倒す。 ・息を吸いながら頭を後ろにそらす。 ・同時に腰を上に持ち上げていく。(どんどん吸う) ・胴体がゆかと水平になる位置まで持ち上がったところで息を止める。 ・ゆっくりと息を吐きながら 1)の形にもどる。 ・2)と同じく腹筋と背筋を鍛え、二の腕も鍛える。 5) 逆Vの字体操 ・うつぶせに寝てから上体だけを起こし、手のひらと足指先を支点にして身体を床から浮かす。 ・手と手の間、足と足の間は肩幅ほどあけておく。 ・息を吐きながら背骨をそらして上半身を起こす。 ・息を吸いながら腰を中心に上体を持ち上げる。 ・息を吸い続け、体が腰を真ん中にした逆V字型になったら(かかとを床につけたまま)今度は息を吐きながら元の姿勢にもどる。これを繰り返す。 ・1週間もすると5つの中で最も簡単と感じるようになる。 6)の儀式 - 活発な性エネルギーを変容させる。なければこの儀式はできない。 性エネルギーを上昇させ、精神力を増し、肉体を若返らせる。⇒性的快楽の放棄 第一のチャクラで生まれたエネルギーを上昇させ、上の全てのチャクラに送り込む覚悟 放散せず、抑制せず、コントロールする方法 過剰な性エネルギーを感じたときに行うべきもの ・まっすぐに立つ。 ・息を吐きながらゆっくりと上体を倒す。 ・ひざに手がつくところまで上体を倒した時点で息を全て吐き切る。 ・そのまま呼吸を止めて、上体を起こし、腰に手を当てる。 ・手を下方に向かって強く押し、同時に煮腹部を引っ込め、胸を引き上げる。 すべての内臓を上の方に持ち上げるようなつもりで。 ・息を止めながらできるだけこの姿勢を保つ。 ・呼吸の停止が我慢できなくなったら、そのままの姿勢で鼻から胸一杯息を吸う。 ・口から息を吐きながら手を下ろす。 食事について ・でんぷん類と肉類を同時に食べない。 ・コーヒーはブラックで。気になるなら食事からはずす。 ・食べ物を液体状になるまで噛み、食べ物の摂取量を減らす。 ・毎日1回生卵の黄身を食べる。(食前か食後) ・1度の食事で摂取する食物の種類をできるかぎり減らす。 若さの泉 チベット体操 ピーター・ケルダー 参照 ●筋肉をつける⇒脂肪を燃焼しやすい体質を作る。 筋肉の働き⇒体を形作る、体を動かす、血液の循環をよくする。 食べ過ぎや肥満(脂肪)にやられない体質を作る。⇒筋肉量と酸素⇒脂肪を燃焼 激しい運動は25歳まで。 ・25歳を過ぎたら脂肪を燃やすゆるやかな運動。 ・30代以降はストレッチ体操 ・ウォーキング-1日トータル1万3千歩-日常生活=1万〜8千歩が目安。 ウォーキングを理想的なエアロビック運動にするには約4.8キロを休まず45分で歩く。 呼吸数があがらないなら歩調を早める、腕を振る、もっと長い距離を歩く。ゆるい坂道をのぼるなどの工夫 最低5千歩、右脳をはたらかせ、視覚や嗅覚などの情報を得ながら歩く。 運動の後は急にやめない。 体が喜ぶ自然で適度な運動を ・仕事は「端楽」。自分の体も大切に。 ・日常生活の全て、家事も仕事も運動療法につながる。人間は歩くようにできている。 ・体質をカバー - 便秘を治す、冷え性の緩和など ・立ち仕事、座業など仕事で長時間同じ姿勢を保たざるをえない場合のケアを考える。 ●運動しながら右脳を使う、瞑想法を取り入れる。 歩く他にヨーガ、気功、太極拳、エアロビクスなどを取り入れる。 音楽を聞きながら… ●呼吸法の5つの訓練を取り入れる。
●一番簡単で自分でできるのが免疫力を高める「爪もみ療法」 呼吸法と爪もみ療法とを組み合わせるのもよい。 ⇒ 詳しくは ■(4)生活習慣・免疫療法・その他へ ●姿勢は他人の目ではなく自分自身のために気をつけて直す。 足を組んだり、横座り、手枕など、骨の歪みの原因になる姿勢を習慣としてとらないほうがいい。 体の片方を使うスポーツも 体の痛みは早めに解決 身体を冷やしすぎないようにし、どの部分も無理に揉んだり、叩いたり、強く押したりはしないで。 ●アンチエイジングのための PPK運動=ピンピンコロリ運動 ・この造語は長野県の公式ページで「当県は平均寿命が長い割に一人当たり老人医療費が全国最低で 『ピンピンコロリの里』と 言われている」と記したのが最初。 (※予防に力を入れ、病人には高度医療や入院は短く集中し、早く退院させ、民間医療機関の夜間の往診を可能な体制をしいた) 「昭和54年、長野県下伊那郡高森町で開かれた県の体育学会で、 高森町内の中高年齢者の 体力・健康づくりのキャッチフレーズとして利用した。 ・運動の中心に東洋医学のツボを利用した。 ・PPKが全国的に知れわたったのは平成10年秋、医事評論家の水野肇氏他編著『PPKのすすめ』出版による。 |